 |
|
|
| ■ |
Technical Support
|
|
|
| ■ |
Technology
|
|
|
| ■ |
Examples
|
|
|
| ■ |
Theoretical Basis
|
|
|
|
|
|
解析手法の概要
受託業務においては,解析対象と検討内容に応じて,通常は完全3次元立体解析,3次元積層シェル解析,ファイバーモデルに基づく3次元骨組み解析(以上,コード名COM3),2次元平面解析(コード名WCOMD)を適宜選択して適用しています.これらは,いずれも”任意の載荷経路依存性を考慮したRCの平面材料構成モデル(及びそれから次元を落とした1軸材料構成モデル)”を基幹としている点では共通です.
この平面材料構成モデルこそが,ひび割れ→降伏→終局へと至るコンクリート構造物の非線形構造応答評価技術の根幹をなすものであり,東京大学コンクリート研究室で長年に渡って開発に取り組まれてきました.
載荷履歴依存性を忠実に考慮し,当初より適用範囲に制限を設けない形での材料構成モデルの定式化を目指してきたことにより,任意の形状・任意の静的および動的繰り返し荷重に対して適用可能である特長を有しています.また,実用化にあたっては,数値解析的な安定性・収束性向上にも力を入れており,近年この点においても大きな成果が挙がってきました.
これまでに,原子力機関等を含めた各種構造物・部材に対する適用や検証,解析技術のコンペティション参加等を通して,国内外で高い精度を有することが実証され,高い評価を受けております.(解析適用例のページに,具体的な検討例を一部抜粋して紹介させて頂いております.)
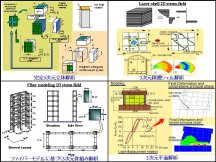
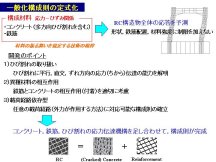
クリックすると拡大されます.
平面材料構成モデルでは,コンクリートと鉄筋の平均応力−平均ひずみ関係から算出した平均応力の重ね合わせにより,応答が算出されます(下図).ここで,”平均”という言葉は,局所的に発生するRCの複雑な応力・ひずみ状態をひび割れが複数分散して導入される程度のボリューム内で空間平均化して表現していることを示しています(=分散ひび割れモデル).
2軸応力下のコンクリートの面内構成則は,ひび割れる前の弾塑性破壊モデル,および,ひび割れ面に沿った圧縮挙動とせん断挙動,それと直交する引張挙動からなります.RC構成則では,鉄筋とコンクリートが組み合わさる相互作用効果(付着)を考慮することが非常に重要となりますが,RC中のコンクリートと鉄筋の挙動はこれを包含して,単体の挙動とは異なる形で定式化されています.
コンクリートのひび割れの扱いについては,ひび割れ履歴に忠実に基づいて,最大4方向までのひび割れを考慮できる(=多方向固定ひび割れモデル)ことが本解析手法の利点の1つであり,精度の向上と適用範囲の拡大に貢献しています.
また,分散ひび割れモデルを基軸に据えながらも,破壊力学的知見を取り入れることにより無筋コンクリートに対しても適用可能な形に展開しているとともに,鉄筋配置に粗密が生じる大型構造物の評価精度を向上しています.(このことは,せん断破壊の寸法効果を考慮する上で重要なポイントとなりました.)
さらに近年では,鉄筋の座屈を表現する構成モデルやコンクリートの軟化則に時間依存を考慮するモデルを構築することにより,最大耐力以降の高非線形領域の解析精度向上を達成しつつあります.
この他,面部材に適用する鋼板等のモデル化もなされているとともに,部材接合部および異種材料間に挿入するための接合要素を各々定式化することで,実用性の向上を図っております.解析手法のさらなる詳細につきましては,参考文献1),2)を御参照下さい.
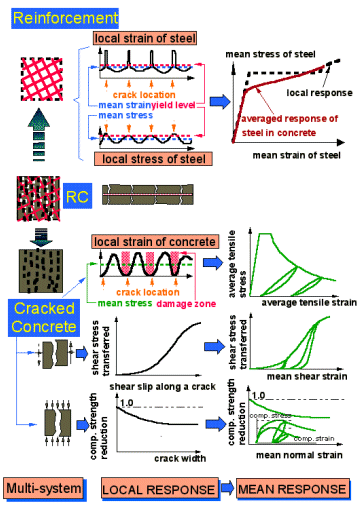
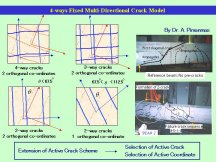
クリックすると拡大されます.
参考文献
| 1) |
岡村甫, 前川宏一:鉄筋コンクリートの非線形解析と構成則,技報堂出版,1991. |
|
| 2) |
Maekawa, K., Okamura, H. and Pimanmas, A.:Nonlinear Mechanics of Reinforced Concrete,SPON PRESS,2003. |
|
|