 |
|
|
| ■ |
Technical Support
|
|
|
| ■ |
Technology
|
|
|
| ■ |
Examples
|
|
|
| ■ |
Theoretical Basis
|
|
|
|
|
|
DuCOMとの統合化
東京大学工学部社会基盤学科コンクリート研究室では,解析技術をさらに発展させる形で,コンクリート構造物の非線形構造応答をシミュレーションする構造応答解析システム(コード名COM3 およびWCOMD)と,
セメント硬化体を形成するナノメータースケールのC-S-H ゲル粒子群からなる無機複合材料の微細構造モデルと物質平衡・移動解析システム(コード名DuCOM)の統合を進めています1)〜4)など.
水とセメントの水和開始から,供用開始,維持管理を経て,廃棄・リサイクルに至るでの挙動をシミュレーションする構想であり,まさにコンクリートの「ゆりかごから墓場(再生)まで」の"ふるまい"を予測する手法の確立を目指すものです.
これまで個別に発展してきたとも言える「材料」,「構造」,「施工」といった壁を一旦取り払い,全体を俯瞰する観点から有機的で合理的なシステム再形成を追求できることが,統合化の最大のメリットであると考えられます.
と同時に,新設および既存構造物の設計・照査等の合理化やライフサイクルアセスメントに対して適用可能なツールともなり,(海外を含む)他の追随を許さぬ極めて強力な情報を得ることが可能となることも見逃すことのできない重要なポイントとです.
例えば,海岸部に存在し,設計想定時を上回る活荷重下にある構造物が兵庫県南部地震クラスの地震動を受けたらどうなるのかと言った,複合要因による問題を統一的な枠組みの中で評価できるようになり,合理化の追求や明確な(特に市民への)説明を果たせる可能性も考えられます.
あらゆる条件下での任意構造物の一生を予測できるようになる(=ライフスパンシミュレーション)までには,ハード・ソフト両面の発達が必要で,もうしばらく時間を費やす必要がありますが,2つのシステム統合化に関しては既に枠組みの構築を終えて,個々の要素技術の製作または向上に取り組む段階に入っております.適用可能な対象も徐々に増えつつあり,日々整備が進められております.
これまでに,PC長大橋梁の長期たわみ挙動や塩化物イオン浸透を受けた構造部材の耐荷性能/動的挙動,トンネル覆工コンクリートのひび割れ進展等に対する検討事例が報告されています.
なお,コムスエンジニアリングでは,DuCOM のフルバージョン(非売品)を使った材料挙動に関する解析サービスも,別途お引き受けしております.
※この内容につきましては随時Updateされている状況ですので,詳細は下記参考文献の他,各種文献またはコンクリート研究室のウェブサイトにて御確認下さい.
また,日本コンクリート工学協会発行のACT誌に掲載された招待論文(2003年)3) が,本テーマを網羅する内容となっております.
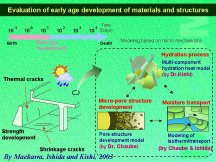
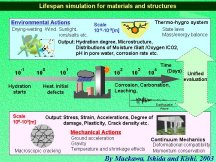
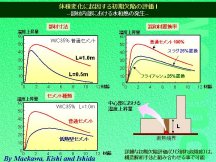
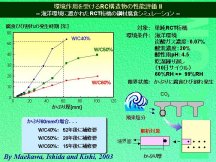
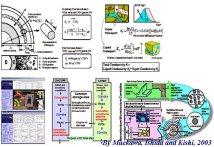
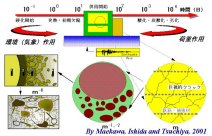
クリックすると拡大されます.
参考文献
| 1) |
Koichi MAEKAWA, Rajesh CHAUBE and Toshiharu KISHI:Modelling of Concrete Performance Hydration, Microstructure Formation and Transport, E & FN SPON, 1999. |
|
| 2) |
Maekawa, K., Okamura, H. and Pimanmas, A.:Nonlinear Mechanics of Reinforced Concrete,SPON PRESS,2003. |
|
| 3) |
Koichi MAEKAWA, Tetsuya ISHIDA and Toshiharu KISHI:Multi-scale Modeling of Concrete Performance -Integrated Material and Structural Mechanics, Journal of Advanced Concrete Technology, Vol. 1, No. 2, pp.91-126, 2003. |
|
| 4) |
前川宏一,石田哲也,土屋智史:非線形解析技術 −ナノからマクロへの連携−, プレストレストコンクリート −PCとコンクリート構造−,Vol.43, No.2, pp.43-49,プレストレストコンクリート技術協会, 2001.3 |
|
|